〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
定休日 :日曜日
発達障害のこと
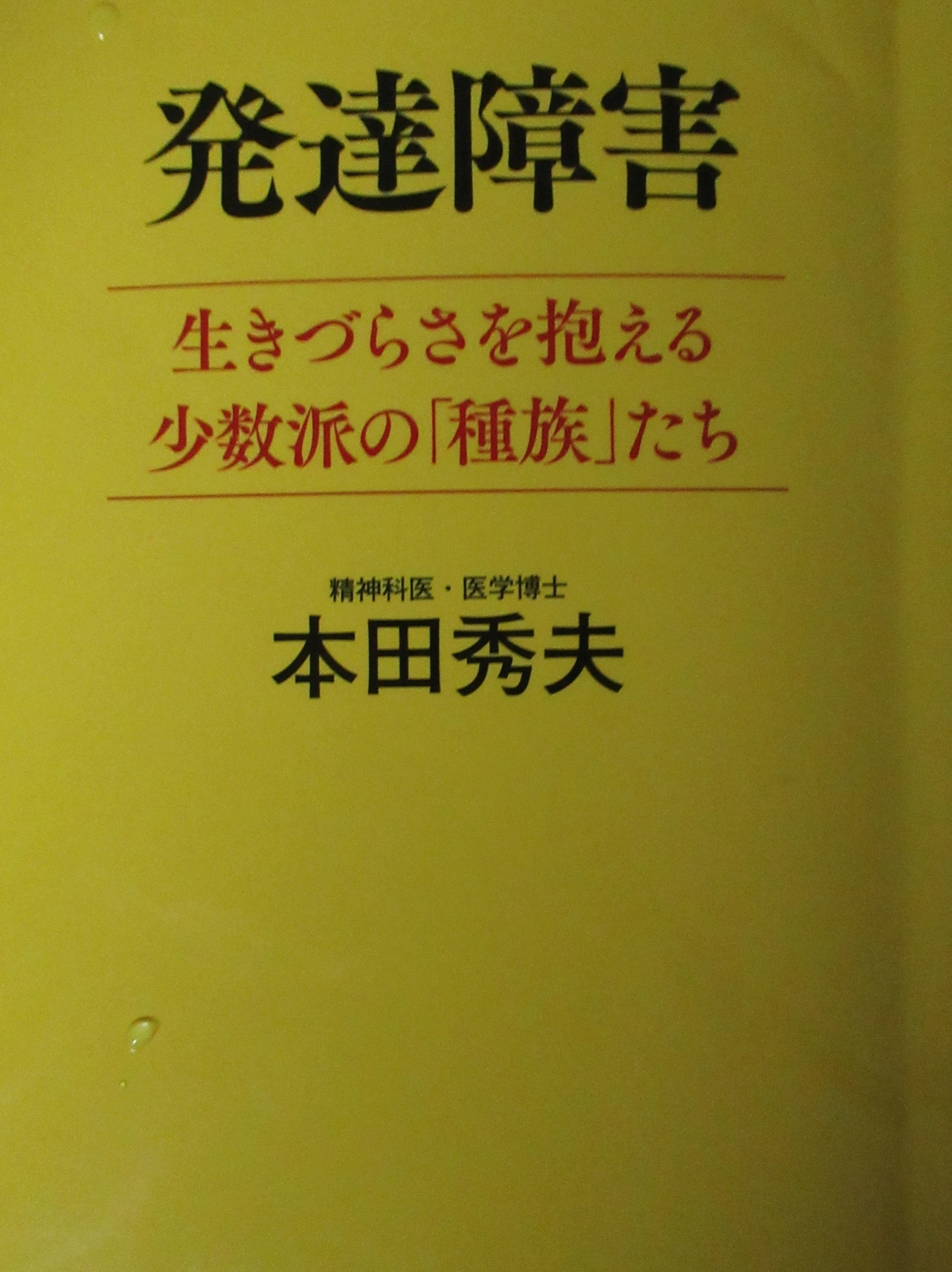
発達障害の人がほかの多数の人違うのは、どんなところなのか、生きづらさなどを紹介しています。
■ 発達障害の「生きづらさ」
「わたしは発達障害ではないでしょうか?」と訴えて、医療機関を受診する「大人」が日を追うごとに増えている。
「子供のころから他人とは少し違うと思ってやり過ごしてきた」。社会人となって、「人付き合いが上手くできない」、「人の気持ちを推し量ることができない」時間管理が上手くできない」と。社会人となることで、「人とのかかわり」が増え、日常生活、社会生活で遭遇する事態にうまく対処できず、「生きづらさ」を抱え、不安になって受診する人、会社から「発達障害ではないか」と受診を促される人が増えている。そんな『発達障害』と障害年金について、少し説明したいと思います。
しかし、発達障害は、「集団活動ができない」、「仕事の段取りが悪い」などとネガティブな表現だけでは説明できない障害です。
発達障害の人たちが「生きやすい社会」になることが求められる社会が近い将来くるはずです。
ここでは、働くことと障害年金についてもお話ししたいと思います。
障害年金診断書のポイント
■ 発達障害での初診日は、「知的障害」があるかどうかで違ってきます
| 発達障害と知的障害の併発パターン | 初診日 |
|---|---|
| ① 知的障害(2級以上)+発達障害 (療育手帳を交付されている) | 出生日 |
| ② 知的障害(3級相当)+発達障害 | 出生日 |
| ③ 知的障害(3級不該当)+発達障害 | 発達障害の初診日(別の病気扱い) |
| ④ 知的障害は無し(発達障害のみ) | 発達障害の初診日 |
本来、障害年金申請の病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を「初診日」としますが、発達障害の場合、「知的障害」の有無とその重症度で、その「初診日」が違ってきます。
■ 発病から現在までの病歴
■ 発達障害が判明した経緯が書かれていますか?
| 発達障害は、社会人になって就職してから判明することがあります。この場合、「初診日」が厚生年金になることから、幼少期に判明した人と年金の金額が変わってきます。(障害厚生年金) |
▶そのため、知的障害を伴わない発達障害の場合は、特に判明したきっかけと、「初診日」まで
の経過が大切になってきます。
■ 発達障害が「知的障害」を伴わない場合のポイント
| ① 発達障害が判明したきっかけ ② 小児期に見られた発達障害をうかがわせる症状や行動 |
▶ 例えば、①について
| 彼女は、ADHD(多動性、注意欠如)の特性で、一言でいえば、「うっかりミス」が多い。物事に対して適度に注意を向けることや、注意を向け続けることができない。 人の話を聞きもらすことや、ものをなくすことがよくある。また、作業をやりきることや、順序立てて進めていくことが得意ではない。仕事をすると、周りから「段取りが悪い」、「要領が悪い」と言われる。 同じ失敗を繰り返し、臨機応変な人とのかかわりができない。会社からは「問題社員」扱い。大きな問題を引き起こすだろうとみられた存在だった。上司に「発達障害」を疑われ、精神科に受診するように指導された。 |
▶ ②について
| 忘れ物はよくしていたし、約束をすっぽかしたり、じっと座っていられず、よく注意されてはいた。しかし、授業の邪魔をするほどではなかった。思いつきでしゃべることがあり、7父親によくしかられた。しかし、成績は悪くはなく、人に迷惑をかけるというほどでもなかったため、見過ごされた。 |
■ 発達障害が知的障害を伴う場合のポイント
| ① 現在までの病歴や成育歴 ② 治療があれば、その経過、その治療内容 ③ 学歴・就労歴(養護学校などに在籍したことがあるかどうか) |
発達障害は「知的障害」を伴う場合、伴わない場合も
出生時にさかのぼって記述する必要があります。

■ これまでの発育・養育歴
▶ 知的障害を伴う場合
| ① 知的障害を伴う場合は、教育歴 「特別支援学級」あるい |
| ② 療育手帳の交付がされているかどうか |
▶ 知的障害を伴わない場合
| 発達障害の人の中には、IQが非常に高かったり、高学歴の人がいます。その場合には、教育歴葉「普通学級」「大学卒」と記入したうえで、他の欄に、対人関係、意思疎通などでの社会人としての「生きづらさ」や「不適応な行動」で、問題社員として見られていることを、具体的に記述されているかどうかが重要です。(以下に)
|
知的障害を伴わない発達障害は、社会的な行動や意思疎通能力の障害が
顕著であれば、それを考慮する(等級ガイドライン)

■ 仕事のこと(短期間しか仕事が続かないなどが記載されているかどうか。
| 発達障害の場合、職場に適応できず短期間のうちに転退職を繰り返すことがあります。そのような場合、職歴だけではなく、短期間しか就労できなかったことが書かれている必要があります。 |
▶ 例えば
| 話をちゃんと聞いていない、うっかりして物忘れをするなどといった特性は小さいころからあったが、社会人になると、重要な話や責任を負わされる。場の雰囲気を壊すような言動なども目立ち、対人県警も築けず、孤立してしまい、仕事への支障は、入社してすぐに表れた。 物事に注意を向け続けることができないため、仕事に集中できず、ミスが続く。自己退職に追いやられ、転職を繰り返さなけばならない。 |

▶ このように記載されてもいいと思います。
| たとえば、社会人(正社員)として仕事に就くも、対人関係や意思疎通ができず、遅刻も多く、配置換えなどの配慮も行われたが、その仕事も、仕事に集中できないため、ミスも多く、「問題社員」扱いされ退職に追い込まれた。 その後、「コンビニやガソリンスタンド」などでの」アルバイトを経験。しかしいずれも、「やりたいこと」ではないため、ミスを繰り返す。どれも、1か月と続かなかった。対人関係が築けないなどのコミュニケーション不足も原因だった。 |
具体的に診断書に記載されているかどうか。
対人関係や意思疎通の困難さも重要です。
▶ 対人関係や意思疎通の難しさが記載されているかどうか。
具体的には、困った時に他人に助けを求めることができない。指示に従った行動がとれないなど。
| 職場では、 ① 常識で考えることができない。 ② 臨機応変に対応できない ③ ミスが多い ④ 接客ができない ⑤ 話し言葉が分からず、聞き取れない ⑥ 環境が変わるとパニックになる ⑦ 「あれ」、「それ」などの指示代名詞や「適当に」などの程度がわからない |
日常生活能力や評価について
■ ひとり暮らしを想定して評価されているかどうか
| 親族(父母)と同居している場合は(一人暮らしは未経験)、特に、「甘い評価」を医師に伝えている場合が多い。少しでも「できる」と思い込む父母感覚を医師に伝わっていれば、医師は素直にその父母や本人の評価を記述します。 |
現在の就労状況について記す場合
新型コロナ禍で「在宅ワーク」というスタイルも確立されました。しかし、発達障害の人の場合は・・・。
■ 具体的な仕事内容を医師に書いてもらう。
| ① 単純な反復作業か ② 上司や同僚の指示に従えるのか ③ 不適切な行動は無いか ④ 臨機応変の対応はできるか ⑤ 常に指導は必要か など、問題点があれば診断書に書いてもらう。 また、補足部分があれば、「病歴・就労状況等申立書」で説明する。 |
自分の特性を知って働くこと

■ 自分の特性を知って働くことは重要。職場環境も応援してくれる
「障害者雇用促進法」が、2016年4月に改正され、障害者の雇用について、障害者の「働きやすい環境づくり」や「差別的な待遇をしない」などと事業所側に義務付けた。また、2018年4月には、事業所が障害者を雇入れなければならない「障害者雇用率」を計算する上で、精神障害者が含まれることになった。(特に「発達障害」についてです)
■ 障害者を雇用するように決められた人数(全従業員対する障害者の割合)
| 事業所などの区分 | 障害者雇用率 |
|---|---|
| 民間企業 | 2.2%(2018年3月までは2.0%でした) |
| 国・地方公共団体、特殊法人等 | 2.5%(2018年3月までは2.3%) |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.4%(2018年3月までは2.2%) |
企業等の障害者に対するバリアフリーを義務づけているのです。
このため、ハローワークによる障害者の職業紹介数も10年前に比べ2倍近い数になっている。
▶ つまり、「働く場」は大幅に増えた。
しかし、「私は、発達障害です」と言って就職できる環境づくりはできたということ。
自分の障害を受け入れれば、働く場はできた。一方、障害者の方が障害を受け入れ、自己理解することとはまた別であるとも思われるが、自己を受容し、適切な作業を選択すれば、短時間労働は可能な時代ではある。それが「他者にとって都合のいい自己理解」にならないような支援は重要であることも確かだと思います。発達障害者が持っている「生きづらさ」を軽減できる社会づくが必要であることを私たちに試そうとしているようだ。
▶ 障害者を雇入れるための施設、介助者の配置等に助成金
・障害者作業施設設置助成金
・障害者介助等助成金 など
▶ 職業リハビリテーションの実施
〇ハローワーク(全国544か所に)障害者の仕事をすることで自立)を支援するための窓口などが設置
〇地域障害者職業センター(全国52か所) 専門的なリハビリテーションサービスの実施
〇障害者就業・生活支援センター(全国334か所) 就業・生活両面にわたる支援・相談
「障害者が「イキイキ」としている社会って素敵ですよ」って。
しかし、まだまだ、ゴールは先です。ゴールにたどり着くまで、障害年金に頼ってもいいのではないでしょうか?
▶ 少し働けたからといって「障害年金が不要」ということにはならないと思います。
障害者の方「まじめ」です。就労の影響で、一生懸命で、就労後の日常生活能力が著しく低下する人も多いのです。「微妙な少数派」である発達障害の人たちを分かってほしいのです。「ネガティブ」な特性を伝えておけば、発達障害の人には「ポジティブ」な特性があります。周囲のサポートを得れば、こだわりなどの「ポジティブ」な特性が生きます。
| ① 知能指数が高くても日常生活力は低い(特に「対人関係」や「意思疎通」を円滑にできない。 ② 不適応行動(不注意が多い。衝動的な行動をする。同時に複数のことができない。 ③ 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限がある。 (等級判定ガイドラインより) |


